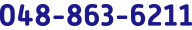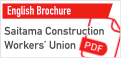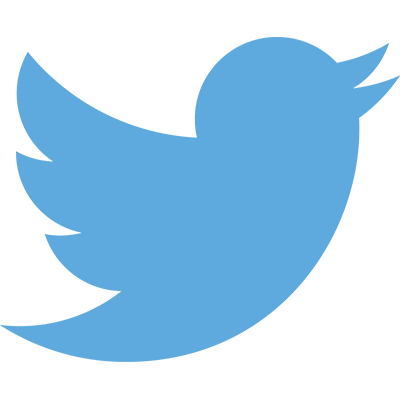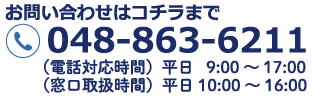お知らせ
埼玉土建の歴史と活動㉕~建設労働組合運動の発展めざし―東日本大震災復旧・復興支援、「応急仮設木造住宅建設」に取り組む
【埼玉土建本部】
つぶやき(学習)
不定期で、埼玉土建の歴史と活動(ダイジェスト)を紹介していきます。
皆さんに埼玉土建の事をもっとよく知っていただけると嬉しいです。
2010年代は、08年秋のリーマンショックを受け、国内総生産(GDP)は長期の停滞状況が続きました。12年12月に発足した安倍政権になっても、17年までの5年間の国内総生産平均成長率は、わずか1.2%にとどまり、特に14年4月の8%への消費税増税で、景気は落ち込み、家計消費は増税前を下回り、深刻な消費不況の状態が続いています。
建設産業は、建設投資が92年の84兆円から2016年の52.5兆円に大きく落ちこみ、建設就業者は、97年の685万人をピークに減りはじめ、17年末は498万人(労働力調査)まで減少しました。
2011年3月11日、マグニチュード9.0の巨大地震が起き、巨大津波とあわせ東北を中心とする東日本一帯に甚大な被害をもたらしました。同時に東京電力福島第1原子力発電所で核燃料が溶解する大事故が発生し、今なお深刻な状態が続いています。東日本大震災と原発事故は、日本の政治・経済・社会のあり方を根本から問い直すものとなりました。
このなかで安倍内閣は、「戦後レジューム(枠組み)」からの脱却をかかげ、「戦争する国」づくりと「世界で一番企業が活躍しやすい国」づくりを強引にすすめてきました。とくに2014年7月に「集団的自衛権行使容認」を閣議決定し、15年9月には、国民多数が反対するなかで「戦争法(安保法制)」を強行成立させ、強権で暴走する政治を加速させました。
この、民意を踏みつけにし、憲法をも無視して立憲主義・民主主義を破壊し、あらゆる分野で暴走する政治に対して、新しい市民運動と「市民と野党の共闘」が発展する新しい時代が始まりました。
【第25回】東日本大震災復旧・復興支援、「応急仮設木造住宅建設」に取り組む
2011年(平成23)3月11日の「東日本大震災」にたいし、埼玉土建は災害対策本部を設置し、国や自治体に救援活動の強化を要請するとともに、組合として救援募金や、救援物資支援、ボランティア派遣等に取り組みました。また埼玉県内に避難した被災者への支援活動をおこないました。
ボランティア支援は、岩手、宮城にのべ53人の仲間が参加、全建総連の家屋応急修繕支援活動で、大槌町、釜石市に5人が7日間通して参加しました。募金と日常品を現地に送り、大工道具・機械類66種293品を岩手建労に送り、復旧・復興活動に貢献しました。
11年7月には、旧騎西高校へ避難している双葉町の被災者を励ます「子ども向け木工教室」ボランティアに取り組み、13年8月、14年9月には、福島のいわきの建設組合と埼玉土建や関東の建設組合共同で、「東日本復興支援住宅デー」(13年105人・埼玉土建45人、14年130人・埼玉土建41人)に取り組んできました。
この復旧・復興支援活動で「応急仮設木造住宅建設」の動きがつくられ、福島県の仮設住宅建設の取り組みに、埼玉土建から次世代の仲間を中心に11人が参加しています。「応急仮設木造住宅」は、被災3県で約8000戸が建設されました。
| チョット補足 「応急仮設木造住宅建設」にむけ、全建総連と全国建築士会連合会、工務店サポートセンターとで、「一般社団法人・全国木造建設事業協会(全木協)」を設立しました。全木協は、災害時に木造の応急仮設住宅を建設する「災害協定」を、各都道府県と締結して取り組みを開始します。関東で初となる埼玉県との「災害協定」を12年3月に締結。埼玉土建は、全木協の一員として、災害時に仮設木造住宅建設に取り組んできました。 その後、16年4月に発生した熊本地震では、全組合員に救援募金と救援物資をよびかけ、現地ボランティア派遣と、熊本県と全木協の協定にもとづく「応急仮設木造住宅建設」に埼玉土建から7人の仲間が従事し、18年7月に発生した西日本の豪雨災害では、8月、愛媛県に5人の仲間が、9月に岡山県に2人の仲間が「応急仮設木造住宅建設」に従事しました。 |
「安心安全なまちづくり」「耐震対策」「災害協定」
大震災を教訓に、まちづくり、住宅のあり方、防災を含め「安心・安全なまちづくり」の活動を強化していきました。
埼玉土建として、自治体による耐震対策を要請してきました。2017年9月現在、「埼玉県建築物耐震改修促進計画」にもとづく「耐震診断助成制度」は61の自治体で、「耐震改修助成」は62の自治体で制度化されました。
自治体との「災害協定」にむけ、地域に精通する建設業者を組織する労働組合として、社会的役割を担う位置づけで、全自治体と懇談と要請を重ねてきました。2012年1月、埼玉土建として初めて「災害協定」を、越谷支部が越谷市と締結し、2018年5月現在、10市5町(猿島地域の3自治体を含む)にひろがりました。
また、2014年8月、埼玉県と「家具の固定化を促進するための取組に関する覚書」を締結し、「埼玉県家具固定サポーター」の登録を開始しました。
| チョット補足 2013年9月、竜巻被害が、越谷、松伏、熊谷などで発生した際には、支部を中心に安否確認と応急処置に取り組みました。松伏町からは応急対策活動が要請され、支部として対応しました。このことをつうじて、災害救助法にもとづき、応急修理をおこなう「施行者リスト」を作成し、対応できるようにすすめました。 |